
彼女に僕が下着を盗んでいることが見つかってしまった。シラを切るには無理なのは明白だった。僕は素直に謝罪した。
警察にでも通報されてしまうだろうか。そうしたら大学や実家に住む両親にまで連絡がいくだろう。
「お宅の息子さんが下着を盗みました」なんて聞いた両親はどんな反応をするだろうか。すぐに家を飛び出して僕のところへ来るはずだ。そして伊織さんに頭が地面に着くほど謝罪を繰り返して――。
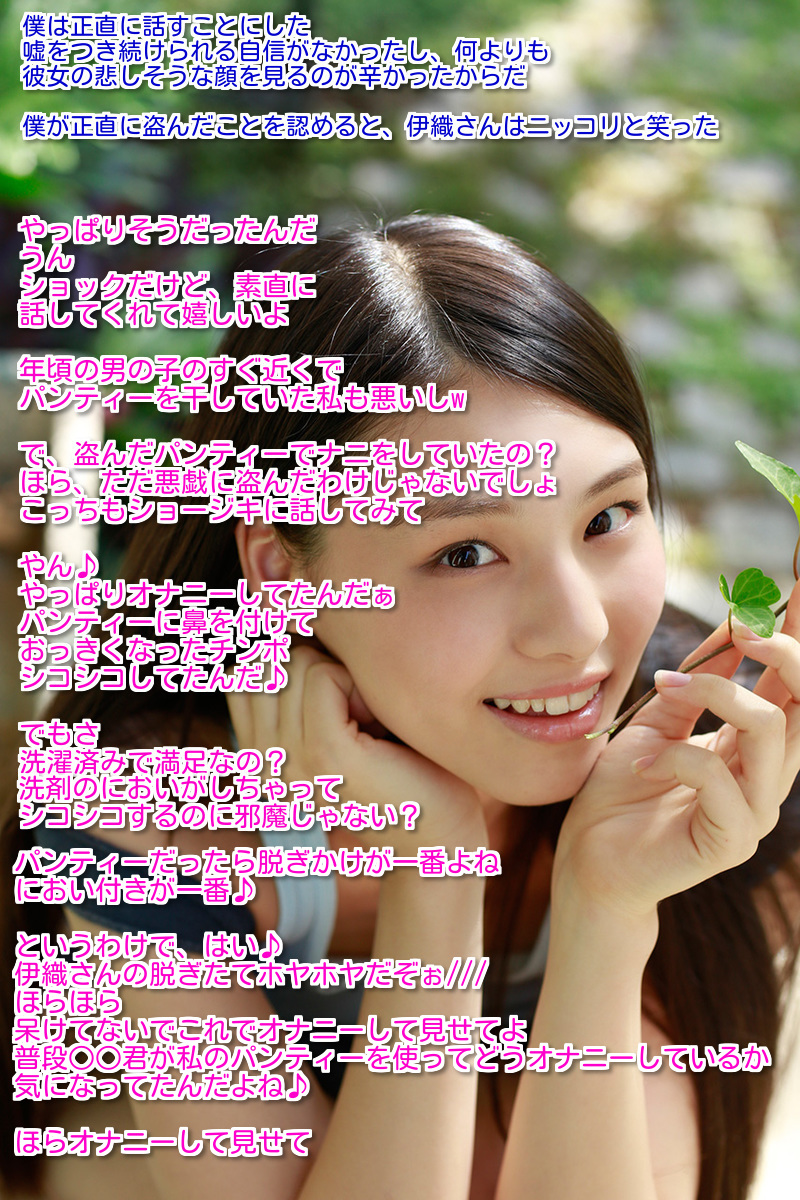
そんなことを考えている僕に対し、伊織さんは予想だにしなかったことを言った。自慰を見せろ、と。
信じられなかった。警察にでも通報されると思っていたのに。
「ほら早く。でなきゃ警察に言っちゃうぞ」
むしろ自慰を見せなければ警察に通報すると脅され、僕に残された選択肢は一つだった。すっかりと縮こまったペニスを見て、伊織さんはフフッと笑った。
そして手渡してきたのが、下着だった。しかも今目の前で脱いだ物だった。
「いつもしているみたいにしてみてよ」
心臓が破裂しそうだった。いつも彼女の下着を盗んで自慰をしていたとはいえ、脱ぎたては初めてだったし、まして人に見られながらするなんて。
興奮が全身を突き抜けそうだった。においを嗅ぐと、いつもなら洗剤のにおいしかしないのに、生臭いにおいがした。
彼女のにおいだ。伊織さんがさっきまで穿いていたこの下着には、彼女のにおいが詰まっている。僕のペニスはいきり立ち、手が勝手に自慰を始めていた。
「へえ。そうやっていつも私の下着を使ってオナニーしていたんだぁ」
アダルトビデオのような世界だった。下着のにおいを嗅ぎながら僕は一心不乱に自慰をした。
「ねぇ、まだ童貞でしょ?」
伊織さんの言葉に僕は自慰をしながらコクコクと頷く。快楽が体中を駆け巡るようだった。
彼女は何か色々と言っているようだった。しかし僕の頭の中は快楽で埋め尽くされていた。何を言っているのかわからないが、とにかく射精に向かって一直線だった。
やがて――
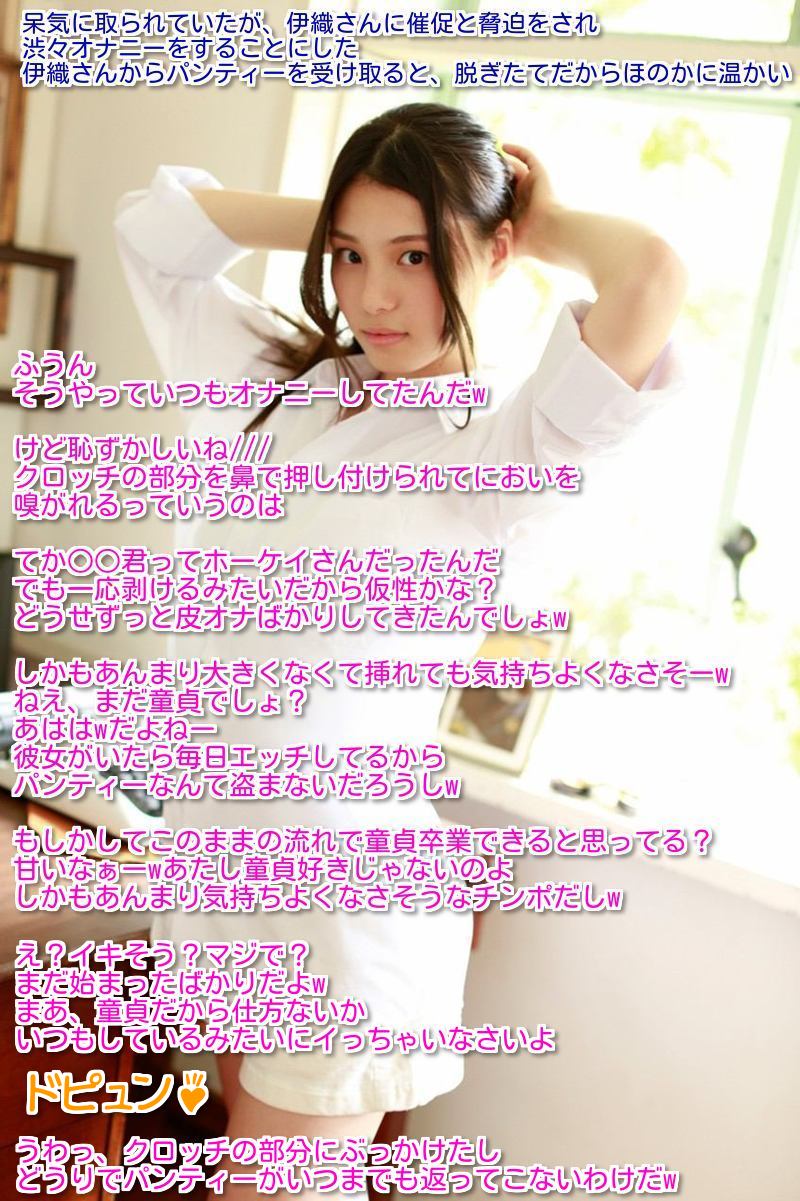
「うっ」
小さな呻き声を上げながら僕は射精した。無意識のうちに彼女の下着に向かって発射させていた。
これまで出したことのない量の精液だった。全てを出し切ると、彼女はニヤニヤと笑っているのがわかった。

アダルトビデオの世界ではきっとこのまま童貞を卒業させてもらえるのだろう。しかし伊織さんから出た言葉は谷底へと突き落とす言葉だった。
彼氏がいる? 警察に言う? 僕は信じられなかった。彼女の言う通りにしたはずなのに。一人暮らしで寂しいから話し相手になっていてあげたのに……。
目の前が真っ暗になった。何も見えない。
ただ、彼女の笑い声と部屋から出て行く音が聞こえた。