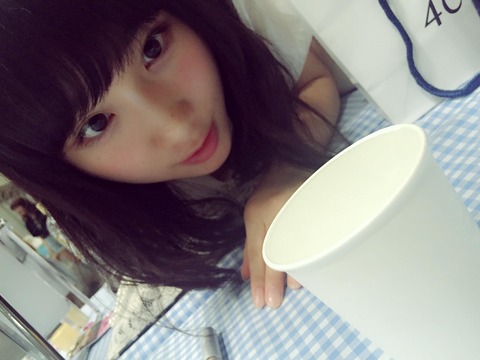
「むっ、あんまり嬉しそうじゃないな」
「いや、別にそういうわけじゃないですよ」
頬に残る、湿った温かい感触。
正樹はようやく朱里にキスをされたのだと、実感することが出来た。
「だったら、もう少し嬉しそうな顔をしたらどうだ」
朱里は恥ずかしそうに頬を赤らめると、唇を突き出しながらそっぽを向いた。
「僕もカクテルを作ってみたい」
いつものように客が朱里一人だけの夜だった。
カクテルを飲んでいた朱里がいきなりそんなことを言い出した。
「カクテルですか?」
「そうだ。簡単そうにやっているから僕にも出来るだろう。だからちょっとやらせてみてくれないか」
正樹はシェーカーとグラスを見た。
「うーん。まあ、作ったものを自分で飲んで、お金を払うというのならいいですけど」
「構わない。じゃあ、そっちへ回るよ」
言うや否や、朱里はカウンターを回って正樹の隣に並んだ。
「説明はどうします?」
「いや、いい。いつも君のやり方を見ているし、なんだって僕にはセンスがあると思うんだ」
「そうですか。なら、お手並み拝見といきましょうか」
余裕綽々といった様子で、正樹は腕を組んで見守ることにした。
「えっと、まずは氷を入れて、次は酒を……」
慎重にシャーカーへと酒を注ぎこむ朱里。
その目は昔作品を手伝ったあの日のように真剣なものだった。
「むっ、零れただと。おかしい。配分は完璧だったはず」
グラスへとシェーカーの中身を注ぎ入れると、無情にもグラスからは中身が溢れ出た。
「そんな一回や二回やった程度では難しいですよ」
「簡単そうに見えたんだけどな。言っちゃあ悪いが、君よりも僕の方がセンスあると前々から思っていたのに」
「そんな目で僕のことを見ていたんですね」
朱里らしいと、正樹は笑った。
「まあ、それよりも味だ。味さえよければ及第点だろう」
中身を零しながら、朱里は自分が作ったカクテルを豪快に飲んだ。
「……不味いなあ」
が、すぐに苦悶の表情を浮かべながらグラスを置いた。
「どれ」
正樹も飲んでみるが、そこに味の調和などなく、単に酒を混ぜただけの味がするだけだった。
「これではお客さんに出せませんね」
「難しいんだな、カクテルって」
朱里はそう言って、恨めしそうに自分が作ったカクテルを見つめた。
「そんな簡単なものじゃありませんよ。さ、気は済みましたか」
カクテルを片付けようとした時だった。
頬に温かく、湿った感触がしたのは。
「そんな気分かと思ってさ」
正樹が問い詰めるよりも先に、朱里は言い訳がましく言った。
「そんな気分? 酔ってるんですか?」
「酔ってる? ああ、そうかもしれないな。今日はなんだか人恋しい日だ。笑いたければ笑うがいい」
そう言って、朱里は正樹に寄り掛かった。
久しぶりに触れる朱里の身体。
昔、成り行きで抱いた時よりも大人の身体つきになっているような気がした。
「別に笑いはしませんよ。ただ珍しいなと」
「僕だって人間だ。人恋しい夜だってある。たまたまだ、たまたま」
「左様ですか」
いつになくお淑やかな朱里。
こうしていれば可愛いものなのに。
正樹はそう思ったが、口には出さなかった。
どうせまた明日にはケロッといつもの彼女に戻っていることだろう。
今は彼女の“そんな気分”に付き合ってあげることにしよう。