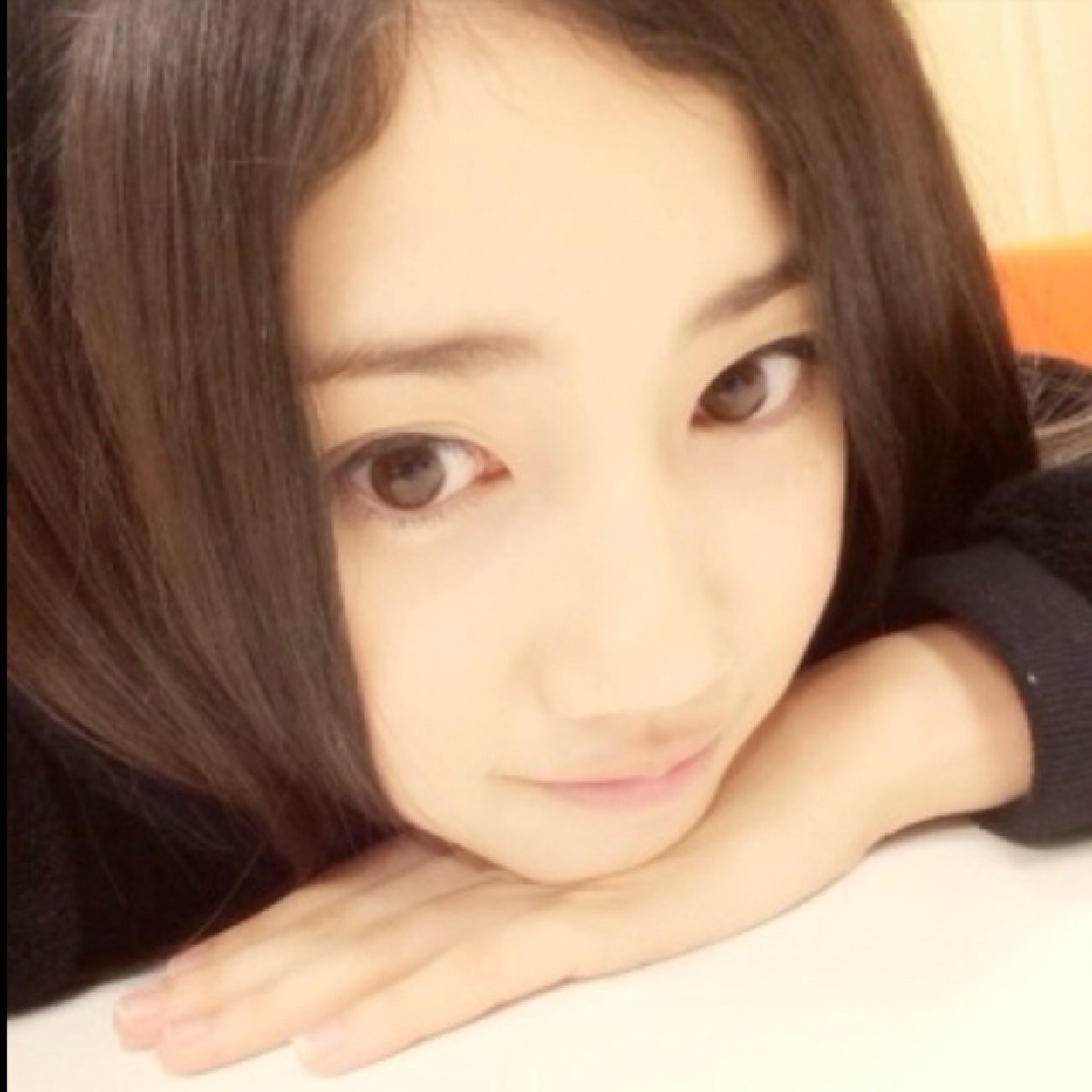
「にゃーにゃー」
学校を終えた北川綾巴は、いつもの場所へ寄り道していた。
彼女の前には、茶トラ模様の猫が一匹、一心不乱に綾巴からもらった猫缶を食べ漁っている。
「美味しいかい? いっぱい食べるんだよ」
小さなこの茶トラの猫は、まるで妹が出来たかのようだった。
いつか母親が入院していた時、自分を習い事の会場から自宅まで送り届けていた彼が言っていた。
「恋」
綾巴は、彼に恋について尋ねたことがある。
彼は言った。
「この人ともっと一緒に居たいと思える人が、『恋』。それを突き抜けた先にあるのが『愛』」だと――。
それからも、綾巴は愛について考えている。
巷で流行っている流行曲。テレビで流れるドラマ。
この世界は愛で溢れ、愛に飢えている。
私は彼のことが好きだったのだろうか。
綾巴の自問は続いた。
恋をして、相手の嫌な部分すらも受け入れられるようになったら、愛に変わる――。
けれども、綾巴はまだ彼の嫌な部分どころか、他の部分すらも知らないことが多すぎた。
「にゃー」
猫缶を食べ終えた猫が、鳴き始めた。
それはまるで綾巴にごちそうさまや、礼を言っているかのようだ。綾巴の胸が温かくなる。
「お腹いっぱいになった?」
しゃがむ綾巴の足に身体をすり寄らせる猫。綾巴はその背を優しく撫でた。
「あっ」
その時だ。
ふと視線を上げた先に見知らぬ男がいた。
男は小太りで、歳は四十を過ぎているようだった。頭髪の薄い頭を撫でながら、ニタニタとした笑みを浮かべ、視線を綾巴に向けている。
男の視線はねばっこく、ある一点を見つめていた。
綾巴はそれがすぐに自分のスカートの中を覗いているのだと気が付いた。
慌てて立ち上がると、猫の頭を撫で、走って大通りに出た。
昼の大通りは車の往来が多く、人通りもあった。さすがにあの男も何かしようとは思わないだろう。
綾巴は一つ息を吐くと、猫に気を取られていた自分を恨んだ。
あんな男に下着を見られるなんて。
きっと彼だったら、許していたことだろう。なんとなくだが。
まだあの通りに戻るのは危険だ。綾巴は買い物をして、時間を潰すことにした。
適当な雑貨店に入ると、音楽が流れていた。
耳を澄ますと、どうやらラブソングのようだ。
この世界は愛で満ちている。
けれども、まだ綾巴は愛を知らない。